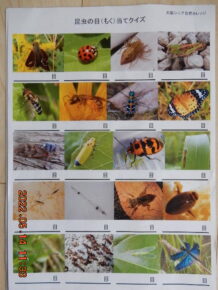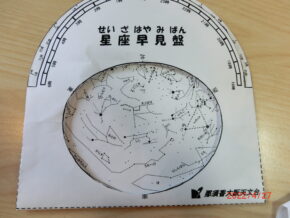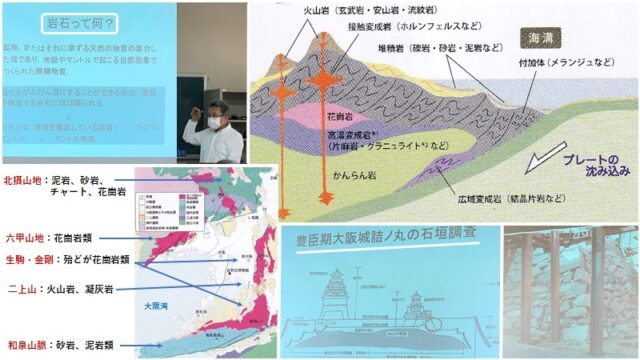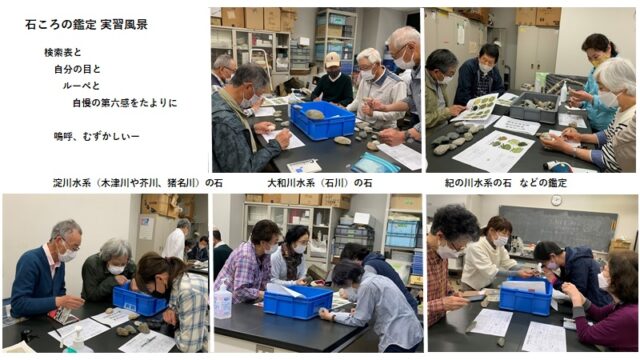月 日:2022年6月8日(水)晴れ
講座名:自然公園の観察①
講 師:武田敏文先生 3名のガイドの皆さま
場 所:くろんど園地
絶好のハイキング日和。準備体操後、3班に分かれて出発。川のせせらぎを聞き、滑らないよう注意して足を進める。白くかわいらしい花が印象的なテイカカズラはつる性の植物。花は初め白く、次第に淡黄色になりジャスミンに似た芳香がある。ムラサキ色の花はタツナミソウ。日当たりを求めて一方向に偏って咲き、とてもかわいい花の形。日本を代表するユリと言われるササユリ。白い花やピンク色の花でひっそりと咲いている。葉がササに似ていることが名前の由来である。
昼食後、自然公園の意義は、自然の大切さを学ぶ環境教育の場であるなど興味深いレクチャーを受けた。後半コースのミズバショウの群生地向け出発。ウグイス、ホトトギスの鳴き声を聴きながら森林浴気分で心地よい。独特の匂いを持つがきれいな花を咲かせるドクダミ、トラの尻尾のようだと言われるオカトラノオなど観察しながら、ミズバショウの群生地に到着。葉っぱの大きさにビックリ!現在約2,500株あるそうで、ミズバショウの見頃は4月初旬。是非また訪れたいものである。
次にモリアオガエルの泡巣がある池に案内してもらう。カエルは水中で産卵するのがほとんどだが、モリアオガエルは水面上にせり出した木の枝などに白い卵塊を産みつける。ガイドさんも初めて見るというモリアオガエルが池の中で、私たちを見張るように卵塊の見える位置に心配な様子でじっとしている。親は大変だ。泳ぐ姿がかわいいく時間を忘れて見入る。今日一番の盛り上がりとなった。ガイドさん達のおかげで、沢山の自然に触れ楽しく充実した講座も終了。本日の歩行距離10㎞ほど全員完歩お疲れさまでした。(N.S)