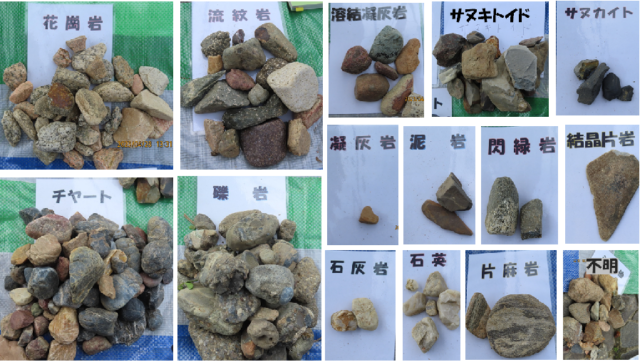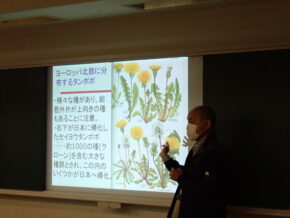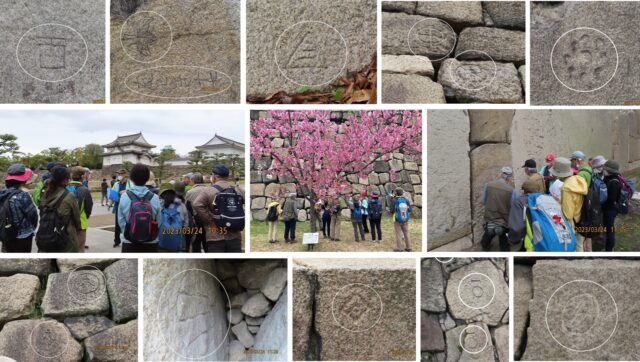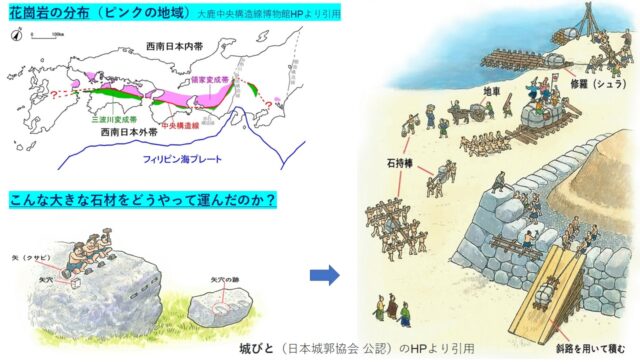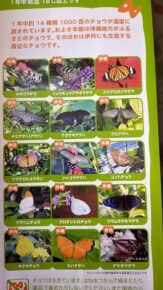開催日 : 令和5年5月20日 (土曜日)
場 所 : 高倉寺 寶積院(堺市指定有形文化財)
句会会場 : 泉北ラボ
参加人数 : 12名
泉北ニュータウンの古刹 高倉寺.寶積院を訪ねました。ここは泉北ニュータウンの玄関口「泉ヶ丘駅』から徒歩で行けます。今日はこの高倉寺 寶積院にある小堀遠州若年の作と伝えられている小庭園、亀の形をしている「亀の庭」と豊臣秀吉がここで茶会を開いた時に「聚楽第」から一字とって「寶聚庵』と命名した茶室を拝観させて頂く予定だったが 茶室は現在使われてなく外から眺めるだけになりました。お庭をしばし観賞して寺内を散策。徒歩で句会会場へ会場のランチボックスを利用して昼食、そのまま自由に句作
オープンなレンタルルームでまた 一味違った吟行でした。(M.T)
・5月兼題 八十八夜・幟・巣立鳥・薫風
・5月会員の代表句
薫風や鯉ひるがえる芥川 尚文
薫風の飛鳥路駆けるニューファミリ たけみつ
風燻る美男で座す阿修羅像 洋々志
ロシアへと帰るも定め巣立鳥 ゆき雄
立漕ぎのセーラー服や青嵐 美枝子
薫風や各駅停車に乗ってみた 河笑流
朝戸開けとまれ目高をひいふうみい 流以
年中の手間を忘るる苺時 都史子
たかだかと武者絵の幟里の庭 楠子
野菜苗を買うて八十八夜かな 万未知
巣立鳥教え子の笑むスクリーン 佐都
風薫る先達ここでひと休み 行行子
・5月当日句特選
青葉風本尊不在新御堂 楠子
・当日句入選
新都市に鎮むる寺や庭涼し ゆき雄
雨上り青葉簾の参詣路 都史子
宝積院菩提の花の髙きかな 河笑流
夏立つや亀の甲羅もさみどりに たけみつ