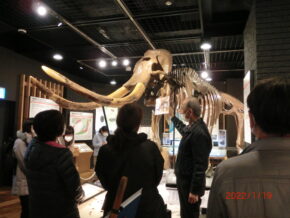年月日: 2022年3月9日 (水) 曇り
講座名: 野鳥観察②
講師 : 久下 直哉 先生・ 日本野鳥の会大阪支部 松岡三紀夫支部長
場所 : 大阪城公園
JR森ノ宮駅に集合し大阪城公園へ。まず市民の森に向かい、樹木にいる鳥・地面にいる鳥の見つけ方の説明を受けた。耳をすまし声を聞き目視する。遠くから近くへと見ていくことが基本を再確認され、大きさ・色・鳴き声だけでなく、歩き方・飛び方・えさなど行動を知ることも大切であると説明され、コゲラ・ツグミ・ハクセキレイ・キジバトなどが見られた。
東外堀ではキンクロハジロがお腹を上に向けてバタバタしているところやカルガモの昼寝が見られ、「可愛い」の声。ナポレオンハットのお洒落なヨシガモ・地味なオカヨシガモ・オオバンやカイツブリ・マガモなどゆっくり観察できた。念願のカワセミは声はすれど姿は見せず、残念でした。
梅の花盛りの大阪城梅林で昼食を摂り梅林鑑賞の後、午後から桜門を抜け日本庭園へ。シロハラ・モズ・メジロ・シジュウカラを観察、オオタカの調理場(ドバトの羽を抜いた場所)も覗くことができた。また、隠し曲輪からは対岸でカラスの群れが水を跳ね上げて行水する様子も見られた。全体として双眼鏡の扱いに慣れて自主的に観察を楽しむ人が増えてきた.
アリスイを観察中の人に遭遇し、観察中の人に対してのマナーもレクチャーいただいた。トータルで(カワラバトを除いて)33種の野鳥を観察して無事に終了した。
松岡支部長から野鳥の会の紹介や、久下先生からのバードウォッチングツアーの紹介などで、講座以外での野鳥観察の機会を知ることが出来た。(T .U)