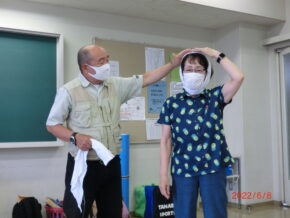月 日:6月24日
場 所:和歌山県橋本市 紀の川(橋本橋の近傍)
参加者:18人
活動内容:
梅雨の真っ只中、晴れはしたものの記録的な猛暑。熱中症が気掛かりだが、橋本駅から紀の川の河原へと足を進めると、北の和泉山地、南の紀伊山脈の間を悠然と流れる紀の川と広大な河原の絶景に息を飲む。源流は奈良県の大台ケ原、奈良では吉野川、和歌山では紀の川と名を変え、紀伊水道にそそぐ大河である。地質学的観点から今回も佐藤隆春先生に紀の川や橋本市周辺の地層の解説をお願いした。当地は三波川変成帯や四万十帯など、多くの地層が入り組んでいることから、上流からの石のみならず近傍の石も入り交じり、その種類も多いだろうと推測される。ひとり2個以上の石ころを持ち寄ることとし、18名の参加者は時を忘れて河原をさまよった。ヨシキリのさえずりも耳に心地よかった。
一か所に持ち寄られた大小様々な石ころの最終鑑定は佐藤先生にお願いした。まとめとして:
- 合計16種類(以下に下線で示す)の石ころが確認された。
- 一番多かったのは四万十帯・秩父帯のチャートであった。チャートはプランクトン(放散虫)の殻が海底で堆積したものであるが、同じ地質帯のものとして他に赤色泥岩や緑色岩も観察された。(赤色泥岩と赤色のチャートは酷似しており、素人には判別困難)
- 2番目に多かったのは三波川変成帯の結晶片岩であった。プレートの沈み込みに伴う高圧により既存の岩石が変成したものであるが、元の岩石や色あいの違いから様々な名称がある。今回は緑色片岩、黒色片岩、珪質片岩、砂質片岩が確認された。
- 他には和泉層群の砂岩、礫岩;領家帯の花崗岩、閃緑岩、斑レイ岩;火山岩類として流紋岩(石英斑岩)や玄武岩質安山岩も観察された。他に緑簾石や石英もあった。20㎝大の岩石の小さな空洞を注意深くみると無数の小さな水晶(石英の結晶)があった。
追記: 写真班の佃さんが撮った河原のヒバリが可愛らしかったのでアップロードしました(ヨシキリだと思ってシャッターを切ったが実際はヒバリだったそうです)。 当月当番の平谷さんから母岩の空洞に見える小粒の水晶群の拡大写真を頂きましたので、それもアップしました。宝石拾いも身近に感じるようになりました。暑くて楽しい一日でした。(I.S)