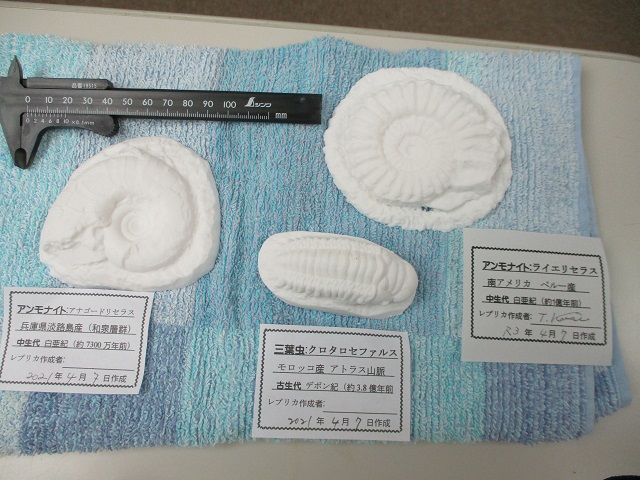1 月日 6月26日
2 場所 松尾寺近辺の里山
3 参加人数 11名
4 活動内容
梅雨空の中、松尾寺に着くとハンゲショウが私達を歓迎してくれた。3ヶ月ぶりの観察なので、花や実を観察出来る植物はずいぶん変わっていた。
A地区(お寺から民家のある所まで)ではウワミズサクラの実が見られた。房状に咲く花はよく知られているが、実を見るのは初めての人が多かった。熟した実は塩漬けや果実酒として食べられるそうだ。日があまり当たらないせいか、ここに咲くキュウリグサもハコベもトキワハゼも花が小さい。21種の花や実のなる植物が観察出来た。
畑沿いのB地区では、草が刈られた後で様子が一変していた。一見よく似ているが異なる、ジャノヒゲとヒメヤブランが近くに咲き、美しい紫のウツボグサ、ピンクの可愛い送りますミゾカクシなどが見られた。また湿った所にしか咲かないヌマトラノオが咲き始めていた。イネ科の植物も多く咲き始め、49種の植物を観察した。
丘に登って行くC 地区では、木本が多く、今食べられるウスノキやヒメコウゾの実、秋に期待できるナツハゼやアケビの実、食べられないイヌビワやサルトリイバラの実も見られた。マンネンダケも参加者の目を惹きつけた。観察後に花合わせをする場所にはピンクのネジバナと薄紫のヒナギキョウ(在来種、キキョウソウやヒナキキョウソウより色が薄く、茎一本に一輪ずつ咲く)が群生していた。また近頃よく見かけるハナハマセンブリの姿も見られた。C地区は雨が降り始めたため急いで観察したが、全部で24種の花や実が観察出来た。最後に3月報告の最後の写真の名前は「アオキの花」です。
(文FK, 写真 RN, SH, YM)
ハンゲショウハナハマセンブリ