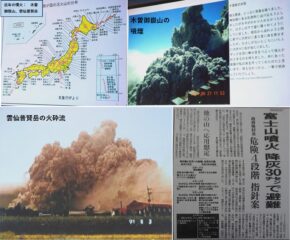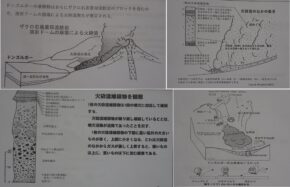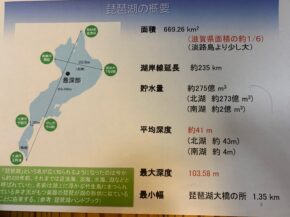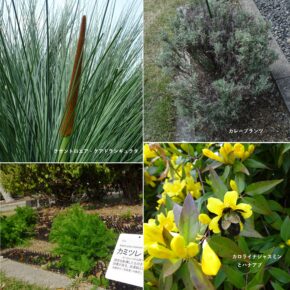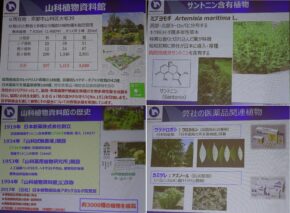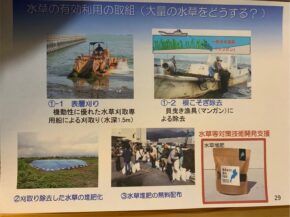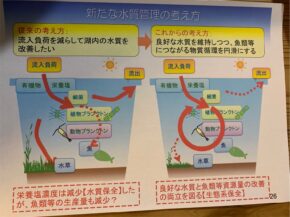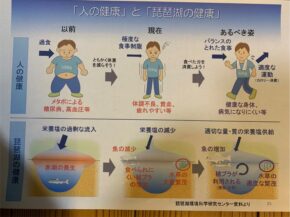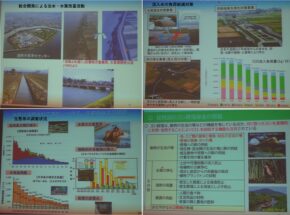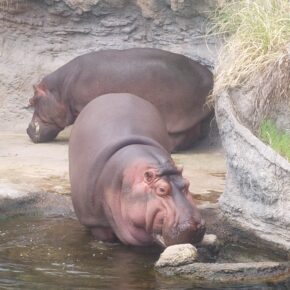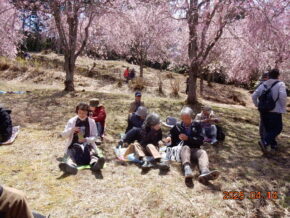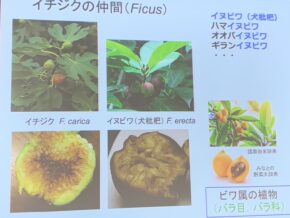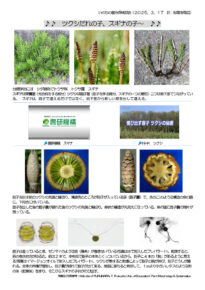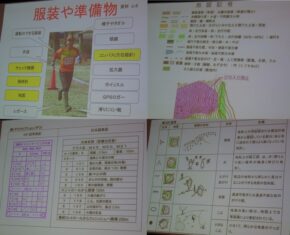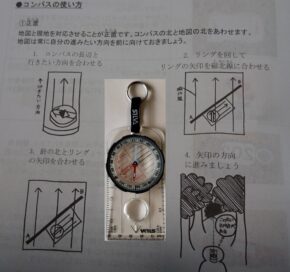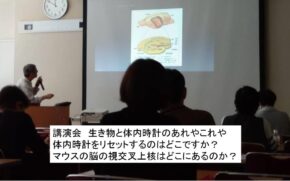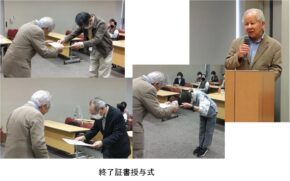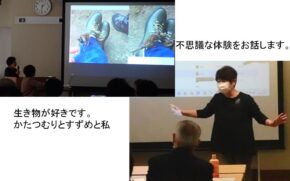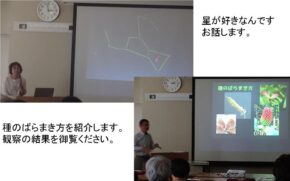テーマ : アメンボを観よう
実施日 : 2025年5月19日(月) 晴れたり曇ったり
観察場所 : 錦織公園
参加人数 : 15名
今日はアメンボの観察。日頃は池や小川に生息するアメンボに目を止める機会がなかったが、今日はじっくりと観察。まずはアメンボの特徴を聞く。
- ・カメムシの仲間で、日本には約30種類が生息。
- ・危険を感じると飴のようなにおいを出し、体が細いことから飴棒(アメンボ)と呼ばれた事が名前の由来(諸説あり)
- ・重さは0.04g、アメンボ25匹でようやく1円玉の重さになる。
- ・脚には細かい毛が生えていて、体内から分泌される油分を足に塗る事で水をはじき、表面張力を活かして水面に浮かぶ。
- ・肉食で、小さな虫が水に落ちた波動を脚で感じ取り、餌とする。
- ・春に水中で交尾し、産卵。卵が孵化すると脱皮を繰り返し成虫になる。
その後、パークセンター裏の石水苑から観察をスタート。多数生息しているアメンボを、小網を使って採取。右に左に動き回ってなかなか同定ができない。 さらにアメンボ池に向かうが、ここでは名前と違って全く姿が見えない。 最後に河内の里の水車脇の小川に移動すると、再び多数のアメンボを発見。 何とか撮影した写真をもとに同定を試み、「コセアカアメンボ」と「ハネナシアメンボ」らしいと推測し、観察を完了。

水面に浮かぶアメンボ達。涼しい顔をして(?)水中に沈まないのがうらやましい。

動き回った後でようやく落ち着いたところを撮影、「コセアカアメンボ」と推定。

写真を拡大すると小さな羽が見える。「ハネナシアメンボ」かな?