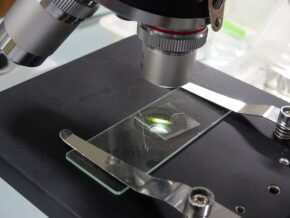年月日 : 2025年7月30日(水)晴れ
講座名 : 高山植物観察・梅花藻の観賞
講 師 : 富岡 秀樹先生 (伊吹山もりびとの会)
場 所 : 伊吹山・醒ヶ井(滋賀県)
今日はバスに乗って、伊吹山と醒ヶ井に向かいます。移動に時間がかかるので帰るのも遅くなりますが、40度に迫る下界とは異なる標高1377mの涼しさに期待です。 三国ヶ丘を出発し、バスの中で伊吹山の四季の植物について事前学習をしました。
山頂駐車場で周囲の山々や琵琶湖を見て記念撮影。ガイドの富岡さんの説明に耳を傾けながら120mの登山です。約1㎞の西登山道にはたくさんの高山植物(紫のルリトラノオ、ミヤコアザミ、ピンクのシモツケソウ、カワラナデシコ、クルマバナ、黄色のキオン、メタカラコウ、白いヤマホタルブクロ、コバノミミナグサ)が咲いていて、色も形も種類も様々で豊富な高山植物が観察できました。また、大昔は海底だった証のウミユリの化石を見ることができ、山頂手前には大きな鹿よけの柵が設置されて、シカの食害の実情も想像できました。
好天に恵まれ、周囲の山々がきれいで、少し涼しい中でのお弁当タイムに、日本武尊像、弥勒菩薩や三角点にも行きました。帰りは急な階段道ですが、中央登山道をおりました。
そして伊吹山を後にして、醒ヶ井宿に向かいました。平成の名水百選にも選ばれた霊仙山から湧き出す「居醒の清水」。そこからの清流(地蔵川)は 、冷たくて手を浸すと暑さをしのいでくれて心地よく、可憐な白い梅花藻も見ごろで美しかったです。醒ヶ井宿の町並みは中山道の趣があり、休憩がてらアイスやかき氷などを食べたりお買い物をしたりして、帰路につきました。懐かしい曲を聴きながら快適なバス旅になり、高山植物と梅花藻の観察で涼しげでたくさんの花を見ることができ、一瞬暑さを忘れさせてくれる楽しい時間となりました。 (M/Y)

山頂を目指しながら高山植物鑑賞

高山植物2

多種多様な高山植物1

積雪の滑り落ち防止柵と鹿よけ柵

山頂風景

頂上付近のウミユリの化石

醒ヶ井1

醒ヶ井2