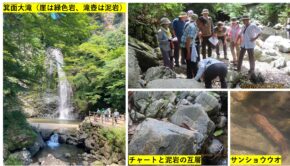実施日 : 2024年7月29日 (月)
観察場所 : 錦織公園
参加人数 : 10名
テーマ : 幸せの青い蜂ブルービーの観察
大阪の予想最高気温が35℃と厳しい暑さの中『ブルービー(青い蜂)の観察』に10名が参加。 ルリモンハナバチ(ミツバチ科)はスジボソコシブトハナバチに寄生するらしい。オオセイボウはドロバチ類の幼虫に。ミドリセイボウはルリジガバチの幼虫に、イラガセイボウはイラガのまゆに寄生する。(以上セイボウ科)等の簡単な説明の後…。ルリモンハナバチがよく現れるアメンボ池近くに向けて出発。途中でキムネクマバチ、タイワンタケクマバチ、トンボの仲間等を観察しながら、アキノタムラソウの群落があるポイントに向かう。
アキノタムラソウの花には、トモンハナバチ、クロマルハナバチ等のハナバチの仲間やクマバチ、ハナアブの仲間が蜜や花粉を求めて飛び回っている。それらを注意深く観ていると、いました青い蜂、ルリモンハナバチが。その後もあちらこちらで見かけたので、写真におさめようと追いかけるがピントが合わず、なかなかうまく撮れなかったのは残念だったが、多くのルリモンハナバチに会えたのでまずまず満足できた。
(今回は観察できなかったがミドリセイボウは特に美しく、岩湧山の四季彩館テラスで出会えるかも)(K.I)
*写真はクリックするごとに拡大され、解像度も上がります。

キムネクマバチ

栃の実の観察

ルリモンハナバチ

ブルービーを探す

ニイニイゼミの抜け殻

タイワンタケクマバチ