月 日:2025年7月23日(水)晴
講座名:ビオトープ入門
講 師:木村 進先生(大阪自然環境保全協会理事)
場 所:大阪府立泉北高校(堺市)
今日は、泉北高校にお邪魔して、ビオトープ池とそこに生きる動植物の観察です。 生物を動物と植物に分けるのは小学校まで。最近では分析などから原生生物界・モネラ界等の5界説、今では3ドメイン説の分類になるそうです。 難しいことはさておき、非常な暑さの中、ビオトープ池に行きいろんな生物を採集して顕微鏡で小さな生物の世界を観察することができました。
中庭で、先生や学生さんが植栽した植物の観察から始まり、ガガブタという変わった名前ながら白い可愛い小さな花が咲いていました。そして、ガマとヒメガマの違いを教えてもらい、小さなエビやオジギソウなど面白い生き物がいっぱいでした。学生さんの育てたスイカは、残念ながら狸の餌食にされたとの話を聞きながらビオトープへ移動。そこは、木陰でかつ豊かな自然のため暑さも緩んだ感じで、各自が池の水や草をスポイトやピンセットを使って夢中になって採取しました。
30分ほどの採集のあと冷房の効いた部屋に戻り、顕微鏡観察を始めました。はじめに顕微鏡の使い方、低倍率レンズを最も近いところから対物レンズを少しずつ離し焦点を合わせることを復習しました。採集した水には、残念ながら見つけることができませんでしたが、先生に準備してもらったサンプルにはたくさんの生命が生きていました。オオカナダモ、元気に動き回るミドリムシやミジンコ、丸い形で中に小さな緑があるボルボックス葉緑体がらせん状のアオミドロ、ワムシ、イシクラゲなど多くのプランクトンを見ることができ、葉緑体の形や状態、ミジンコの卵など興味深いものも観察できました。
その後、高校でビオトープを造成した時の話、管理方法から始まり、ヒシ、ガガブタ、オオミクリ、ジュズダマ、ヨシなど植物が意外にも簡単に育ったこと、ウシガエルの大量発生や招かれざるアメリカザリガニの話など、楽しそうであり、大変そうな維持の苦労話を伺いました。ビオトープが身近になるのは難しいかもしれませんが、自然の維持にはある程度の配慮が必要で、そこには目に見えない小さな生き物たちが元気に生きていることを学びました。 (Y/M)

ビオトープにて

顕微鏡写真
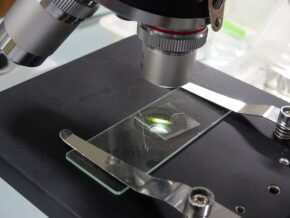
顕微鏡

観察グッズ

カガブタ

ガマとヒメガマ